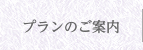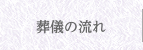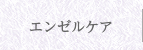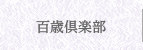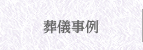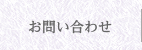HOME > ご葬儀の流れ

●24時間、いつでも結構です。
●ご遺体をご自宅または式場までお送り致します。
●ご遺体をご自宅または式場までお送り致します。
●新しい筆の穂先か、割箸の先にガーゼや脱脂綿を白糸でくくり、茶わんの水に浸して故人の唇をぬらすようにします。
(病院から自宅に帰ってからおこなうことが多いようです。)
(病院から自宅に帰ってからおこなうことが多いようです。)
●肉親や特別な関係の方にはとりあえずお知らせします。
●以後の諸手続きに必要です。必ず忘れずに。
●ご自宅でなくなった場合も、医師または警察による死亡の確認が必要です。
●ご自宅でなくなった場合も、医師または警察による死亡の確認が必要です。
●宗旨・宗派・所属寺院の確認。
●通夜・葬儀・お骨上げ・初七日などのスケジュールを相談します。
●戒名・法名のお願いをします。
●通夜・葬儀の僧侶の人数・送迎・食事などを打ち合わせします。
●火葬場のお勤めの確認をしておくとよいでしょう。
●戒名・法名のお願いをします。
●通夜・葬儀の僧侶の人数・送迎・食事などを打ち合わせします。
●火葬場のお勤めの確認をしておくとよいでしょう。
●神棚の戸を閉め白紙で張り、絵画や額・置物などの装飾品は取はずし、表には忌中紙を張ります。

●町内会長又は組長(班長)に連絡します。

●喪主を決めます。
●通夜・葬儀の日時・式場を決定。
●葬儀の規模と予算を決めます。
●世話役や主な係を決めます。
●通夜・葬儀の日時・式場を決定。
●葬儀の規模と予算を決めます。
●世話役や主な係を決めます。

1.遺影写真の引き伸ばし 2.霊柩車・火葬場 3.会葬礼状・お供養品
4.通夜供養品 5.お柩・葬具一式 6.式場の設営
7.受付用具・案内掲示 8.テント・冷暖房設備等 9.バス・ハイヤー
10.新聞広告・その他
4.通夜供養品 5.お柩・葬具一式 6.式場の設営
7.受付用具・案内掲示 8.テント・冷暖房設備等 9.バス・ハイヤー
10.新聞広告・その他
●死亡届けに必要事項を記載します。 ●死亡届けの手続きをします。 ●(埋)火葬許可証を受け取ります。
●火葬場の手続きが必要な場合は済ませておきましょう。
●火葬場の手続きが必要な場合は済ませておきましょう。

(弊社と通夜・葬儀の日時を決めてから連絡した方が1回で済みます。)
■親戚への連絡 ■友人や関係先への連絡 ■町内への連絡
●通夜・葬儀の日時が決まったら速く連絡しましょう。
●故人や遺族の会社関係には、社内で中心となって伝達してもらえる上司などに連絡します。
●向こう三軒両隣りは、直接あいさつに出向きます。
●町内への連絡は、町内会を通じておこなうようにします。
●重複して連絡されると大変失礼になりますので、よく確認の上連絡する様に致しましょう。
■親戚への連絡 ■友人や関係先への連絡 ■町内への連絡
●通夜・葬儀の日時が決まったら速く連絡しましょう。
●故人や遺族の会社関係には、社内で中心となって伝達してもらえる上司などに連絡します。
●向こう三軒両隣りは、直接あいさつに出向きます。
●町内への連絡は、町内会を通じておこなうようにします。
●重複して連絡されると大変失礼になりますので、よく確認の上連絡する様に致しましょう。

●ご寺院用の座布団、お茶・お茶菓子を準備します。
●受付の場所と人を決めておきます。
●お供養品をお渡しする場所と人を決めておきます。
●道案内(指差し)は適切に設置されていますか。
●履物・傘・携帯品等の間違いが無いように番号札を用意するほうがよいでしょう。
●駐車場も出来れば用意いたしましょう。
●冷暖房設備・テント等の追加の必要性は?
●座布団・お茶・お茶菓子・通夜料理・お酒等、通夜接待のご準備は?
●トイレットペーパーは、眼につきやすい所に十分用意しておきましょう。
●遠方からのご親族の宿泊のご用意は?
●数珠・黒ネクタイ・靴下・貸衣装用の肌じゅばん・足袋・御布施の袋などのご用意は?
●受付の場所と人を決めておきます。
●お供養品をお渡しする場所と人を決めておきます。
●道案内(指差し)は適切に設置されていますか。
●履物・傘・携帯品等の間違いが無いように番号札を用意するほうがよいでしょう。
●駐車場も出来れば用意いたしましょう。
●冷暖房設備・テント等の追加の必要性は?
●座布団・お茶・お茶菓子・通夜料理・お酒等、通夜接待のご準備は?
●トイレットペーパーは、眼につきやすい所に十分用意しておきましょう。
●遠方からのご親族の宿泊のご用意は?
●数珠・黒ネクタイ・靴下・貸衣装用の肌じゅばん・足袋・御布施の袋などのご用意は?

●お勤めの終了後、ころあいを見て喪主または親族代表が挨拶をおこないます。
●お通夜が一段落したら、焼香順位・供車配分など翌日の式典の準備を親族の主だった方々と
相談しておきましょう。
●お通夜が一段落したら、焼香順位・供車配分など翌日の式典の準備を親族の主だった方々と
相談しておきましょう。

●ご葬儀の準備等は弊社係員が適切にアドバイスさせていただきます。
●ご葬儀式典の進行等は全て弊社係員がお世話させていただきます。
●ご葬儀式典の進行等は全て弊社係員がお世話させていただきます。
●隣近所への挨拶 ●お世話になった方への挨拶 ●寺院への挨拶 ●会社や目上の方への挨拶
●寺院との打合せをします。 ●日時、出席者を決めます。 ●料理、引出物の手配をします。
(弊社にお申し付け下さい)
(弊社にお申し付け下さい)
●弔電、供花、供物をいただいた方にはお礼状を出した方がよいでしょう。
●香典を書留等でいただいた方にはお礼状を出した方がよいでしょう。
●町内会などの掲示板に挨拶状を貼ります。
(弊社にお申し付け下さい)
●香典を書留等でいただいた方にはお礼状を出した方がよいでしょう。
●町内会などの掲示板に挨拶状を貼ります。
(弊社にお申し付け下さい)
●身分証明書、保険証等の返却をします。
●給与精算、退職金、社会保険、厚生年金等の確認をします。
●給与精算、退職金、社会保険、厚生年金等の確認をします。
●香典帳の整理をします。
●お返しの品物は香典の1/2〜1/3が一般的です。
●あいさつ状は品物に付けるか、又は郵送します。
●お返しの品物は香典の1/2〜1/3が一般的です。
●あいさつ状は品物に付けるか、又は郵送します。
●日時・場所を僧侶、親戚と相談します。(命日より後には行いません)
●日時が決定したら出席者の案内をします。
●料理、引出物の手配をします。
※忌明法要は故人にとり大変重要なものとされています。
※忌明に白木の位牌を塗り位牌か繰り出し位牌に替えます。
●仏壇がない場合や買い替えの場合は忌明までに行いましょう。
●施主は下座に座り挨拶をします。
●お墓参りをする場合は事前にお墓の掃除をしておきます。
●埋葬の時は、埋葬許可証が必要です。
●浄土真宗では本山の御廟(ごびょう)へ納骨することがあります。
●日時が決定したら出席者の案内をします。
●料理、引出物の手配をします。
※忌明法要は故人にとり大変重要なものとされています。
※忌明に白木の位牌を塗り位牌か繰り出し位牌に替えます。
●仏壇がない場合や買い替えの場合は忌明までに行いましょう。
●施主は下座に座り挨拶をします。
●お墓参りをする場合は事前にお墓の掃除をしておきます。
●埋葬の時は、埋葬許可証が必要です。
●浄土真宗では本山の御廟(ごびょう)へ納骨することがあります。
●遺言の有無を確認します。 ●遺産分割協議書 ●法定相続 ●相続の放棄
●相続税の申告と納付を10ヶ月以内に行います。
●故人の確定申告は相続から4ヶ月以内に行います。
●相続税の申告と納付を10ヶ月以内に行います。
●故人の確定申告は相続から4ヶ月以内に行います。
●国民健康保険加入者は市民課に葬祭費を申請します。
●社会保険、労災保険加入者は埋葬料を勤務先にお願いします。
●国民年金の手続きにより、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかが支給されます。
●葬儀費用の領収証は保管しておきましょう。
●社会保険、労災保険加入者は埋葬料を勤務先にお願いします。
●国民年金の手続きにより、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかが支給されます。
●葬儀費用の領収証は保管しておきましょう。
●仕事関係の書類は5年間の保管が必要です。
●原則として親族で分け、目上の人には分けません。
●帯、着物、背広などは仕立てなおし使うことができます。
●原則として親族で分け、目上の人には分けません。
●帯、着物、背広などは仕立てなおし使うことができます。
●初盆祭壇、盆提灯、迎提灯を準備します。
●寺院と日時の打合せをします。
●年忌法要は、一周忌、三周忌、七、十三、十七、二十三、二十七、三十三、三十七、五十・・・と続きます。
●亡くなった月日の翌年の同じ月日に一周忌をおこない、その翌年(満2年目)に三周忌と数えます。
●寺院と日時の打合せをします。
●年忌法要は、一周忌、三周忌、七、十三、十七、二十三、二十七、三十三、三十七、五十・・・と続きます。
●亡くなった月日の翌年の同じ月日に一周忌をおこない、その翌年(満2年目)に三周忌と数えます。